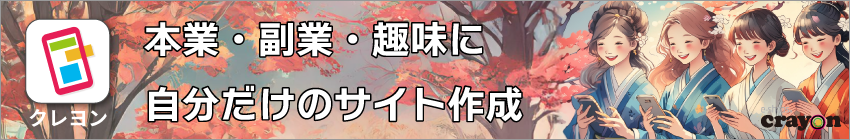発見誌9月号より
2025年発見誌9月号
<巻頭言>とうほくリモート懇談会の発足
各地の集談会や地域の隔たりを超えた活性化のためのZOOMの活用は、とても良い企画ではと思います。各人各人が日本全国で繋がりを持つことは、良いことかもしれませんね。
そして治療家でも研究者でもない私たちが「森田」を本当の意味で体得していくには、発見誌の「はっ犬くん オリジナル森田を読む」の活用も良い方法かもしれません。観念的な私たちにとって、実践し体得することはたいへん難しい課題と思っていて、集談会の話し合いをどう日常生活で生かしていくかは、その人自身にかかっています。後押しできる話し合い、集談会でありたいと思っています。
<名文発掘>治るとはどういうことか(下)
治るとは症状が無くなることではなく、前向きな生活ができることでその中では、不安や恐怖の気持ちもある。前向きで建設的な生活を続ける中で、結果として症状を忘れる機会が増えていくと理解しました。治った状態や治癒の段階についての高良先生の記述があったので整理しました。
「治った状態」
① 建設的作業を続けることができること。
② 物ごとをあるがままに認識することができる。
③ 他人に対して愛情を持つことができる。他人の幸福を喜び、不幸を悲しむことができる。
④ 自省心、反省心というものをもっている。
⑤ 自分の行動に責任を持つことができる。
⑥ 精神的弾力があって融通がきく。
⑦ ユーモアを解し生活を楽しむことができる。
以上は精神的な健康状態を表しているのですが、すべてを持っている人は、このストレスフルな世の中で普通の人でも、あまりいないのではと思ったりしました。
「治癒の段階」
① 症状がまったく消失して社会的、家庭的生活が可能
② 症状が多少あるけれども社会的生活、家庭的生活のまったく支障がない状態(陶治期)
③ 症状のために社会的、家庭的に多少の支障がある状態(軽快)
④ 症状のために社会的、家庭的生活にはなはだしい支障がある。
⑤ 症状のために社会的、家庭的生活がまったく不能である。
集談会に参加される方は②や③の方が多いのではと思いました。自分も含めて究極は①を目指していますが、自己満足に陥るかもしれませんね。
<わたしの森田人間学>「強迫観念」の体験を語る(6)
「不完全恐怖」は、我々神経質者は少なからず持っているのでは?と思っています。
「神経質者の無意識は信頼できる」という言葉、即ち「神経質者の無意識的なおこないは、ものごとにおいて適切な対応ができている」のですが、それでも確認行為(数少ない)は、強迫症ではない神経質者にも、起こる行為なのかもしれませんね。そして山中先生は、相談業務から「自分自身の人生をどう考え、どう生きるか」を学んで行かれたのだと思いました。
そして我々、神経質者はどうしても「生きる意味」という哲学的命題について、深く考える人種なのかもしれませんね。
<体験記>森田と共に生きていきたいー対人恐怖・不完全恐怖―
壮絶で赤裸々な体験記で、いなさんは存じ上げている人かなと思いました。私も会社の人間関係、燃え尽き症候群からうつ状態になり、そして森田を知って回復した経験があり興味深く読みました。自分がうつ状態で出勤すると周りの人達が生き生きと仕事をしているのを見て、自己否定観、自己嫌悪感に襲われていたことを思い出しました。同じような経験をいなさんもされたのだなと感じました。森田を自分のものにするキッカケとして「自分なりの森田でよいこと、森田はあくまでも生きるため指針」という言葉で楽になったという文章が印象に残りました。各人それぞれの森田なんですよね。より良く生きていくための自分なりの森田で良いことを確認できた体験記でした。ありがとうございます。
「集談会・ヒント帳」九州支部
同じ支部の横林支部長の投稿で仲間のためにいろいろと活動されていることを知りました。
感謝します。これからも九州支部の各集談会のますますの活性化を願っています。
<パニックな私の森田な日々>
ゲーム依存症で不登校経験者の方が森田で良くなったのですね。森田理論や集談会の活用が有効だったお話、興味深く読みました。
<生ingセイ・イング> うつ病のQ&A
うつ病について躁うつ病、内因性うつ病、神経症性うつ病の解説、良かったです。自分が抑うつ状態になって、心や体のエネルギーが抜けてふらふら状態を経験したことを思い出しました。そして過去の後悔、将来の不安だけしか考えられず、頭の中だけが緊張状態であったなあと思い出しました。これは「今までの生き方がどこか無理していたこと」で人生の生き方を見直す貴重な感情体験であったのだなと理解できました。この時に森田に出会えて良かったなと改めて実感できました。
<私と森田と発見会>自分の道 発見会そして集談会を歩む
あるキッカケからとらわれに陥った経験、自分の感情はコントロールできるとの思い違いなど、自分も同じ経験したなあと思いながら読みました。また「なりきる」の心境についての具体例は良かったです。そして「集談会の大切さ」に以下の言葉が印象に残りました。
・集談会でよく人の話を聴いていると、必ず新しく聞く森田とか、忘れていた森田を聞くことができるはずです。それが発見会に入って間もない人の話であろうが、はっと気づかされることがたくさんあると思います。
私も人の話を聴くことで自分への気づきが生まれ、生きるヒントを与えてくれると思っています。また自分自身のことはなかなか見えないのですが、同じ神経質性格の仲間の声から自分自身が見えてくることがたくさんあり、学びとなっています。
<モリジイと学ぶ学習会シリーズⅡ> 4.欲望と不安
読者の人達の便りは、一生懸命にモリジイの話を理解しようとする気持ちが伝わってきました。不安の裏には欲望があるので不安感を意識化して囚われたように、欲望を意識化して実現のために役立てることができると良いなと思いました。
「神経質者は白黒つけるのが好き。それはスッキリしたいという気分があるからだと思う」
の言葉は自分自身にも当てはまるなあと思いました。世の中は白黒がはっきりした世界ではありませんね。グレイの部分が多い中でいかに生きていくかを学ばなければいけませんね。それが人それぞれの加減なのかもしれませんね。
「欲望に視点を置いて舵を切れ」の言葉は良かったです。
<学習会参加報告> 第121回 東京基準型学習会
稲垣講師の「コメントを書くときも、批判やアドバイスはせず、ただその辛い気持ちに共感し、受け止めるに務めました」というと言葉が心に残りました。集談会の話し合いでも生かして行ければと自分自身に対して思った次第です。
また参加者の以下の言葉も良かったです。
・皆と同じようにできなくても生きる場が与えられ、受け入れてくれる人がいたら、それでいいかな
・我々の学習は、最初はまず頭で理解しつつも、日々の生活での体験や集談会での体験の分かち合いの中で「ああ森田で言っているのはこういうことか」という小さな体験を積み重ねる、という方法をとります。
・自分を苦しめる・責めている癖、自分を追い詰める癖にも気づき、少しずつ感情を流せるようになってきた。
<中高年のひろば> 本音はどこに
私も森田を学んでいるのに、相変わらず思い込みや「かくあるべし」でがんじがらめになって苦しんでいることがあります。
・「事実」とは、主観と客観の調和である。
・「自分を生きてください」「自分の本音に素直になる」など勉強になる言葉がありました。