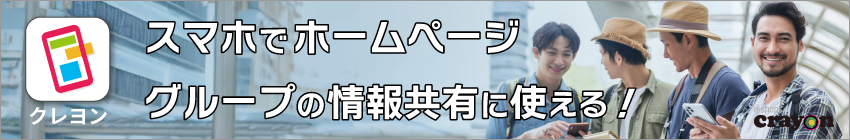発見誌7月号より
<巻頭言>発見会活動を振り返ってみて
「随分遠回りな人生を歩んできていると感じますが、こういう人生もありかなと思うことにしています」の文章に、筆者の自己肯定感、気持ちの余裕、やさしさを感じることができました。たしかに症状が軽くなったら満足してしまい、怠けている期間もありますね。そして理論学習には「森田理論学習の要点」の活用が大事ですね。参考になりました。
<名文発掘>人を不幸にする十二箇条(3)
① 愛するものを持たない
② 絶対主義
③ 過大な要求水準
④ 嫉妬心
⑤ 環境に随順しない
⑥ 依存心
⑦ 自己中心
⑧ 仕事を持たないこと
⑨ 事毎に比較する癖
⑩ 時の経過にさからう
⑪ 節度を守らない
⑫ 病気
「事毎に比較する癖」にハマって、一時期自己否定に陥っていたことを思い出しました。
自分は自分と理解し一歩、前に出ることを忘れていました。
「人を不幸にする要因というものは、ある程度誰でも持っているんです。これを絶対になくすことはできない」の言葉から、我々は、「人を不幸にする十二箇条」に強くこだわりすぎていることが理解できました。結論として「不幸な要因をはびこらせないために、大体のところで前向き進んでいられたら」との言葉がありましたが、各自がそれぞれ工夫するしかありませんね。「活力を発揮して幸福な人生を」のために
<わたしの森田人間学>「強迫観念」の体験を語る(5)
「神経質のとらわれ」については、みずからの不安や恐怖を取り除こうと自作自演をしていることを森田理論は教えていて、「あるがまま」に徹することでとらわれから解放されることは、よくわかります。しかしそのことに気づくキッカケには、時間がかかり人それぞれですね。
山中先生の場合は「どんなに激しい対人緊張がおきても「いっさい恐縮状態そのまま」」を試みたことがよくわかりました。とらわれの気持ちがあっても「おっくうのまま・しかたなしに・やむをえず」に日常生活をきちんと送ることで、恐怖突入の場面が出てきて、気づき(自覚、発見)が得られるのだと理解しました。
<体験記>60歳の今、そしてこれからー臨場恐怖ー
18歳で集談会に出会い、人生にいろんなことがありながら、ずっと続けられていること、すばらしいです、敬意を表します。
「症状を持ちながら生活するという面では以前と同じですが、仲間がいるということを知ったというのは孤独からの解放でした」の文章が心に残りました。集談会に出席し、同じ仲間がいることは助けになりますね。また「症状以外のいくつもの生きづらさ」の項目では、自分にもあてはまるものもあり、だれでもいくつかは持っているのではと思いました。森田理論は理論として、生きづらい人生について、「人生の意味」を自分なりに見つけていくしかありませんね。
今回の体験記の中に懐かしいお名前、Fさんを発見しました。私は症状真っただ中で、FさんやKさんの体験記「燃え尽き症候群そして抑うつ状態からの回復」を読んで、自分も森田療法で回復できるかもしれないと思い、森田療法を学ぼうと決めました。体験記に出会ったことは、今は懐かしい思い出ですし、FさんやKさんに感謝です。
<集談会日記>千葉集談会
宮崎康夫さんの特別講話で
・森田の、過去を悔やんだり、否定したり、懺悔せず、今を生きていくという建設的な生き方の哲学に共感したこと
・どうにもならない自分にいら立ちや焦燥感をずっと感じていた。ある時、ふと苦しみながら、あるがままになすべきことをなそうと努力し、行動している自分がとてもいとおしくなり、誰も褒めてはくれないのだから、せめて自分一人でも褒めてやらなければあまりにも不憫だと感じ、しばらく泣き、嘆いた—-徐々に今の自分を受け入れられるようになり、少し楽に生活ができるようになっていった。
などの言葉が印象に残りました。
この文章からセルフ・コンパッションの話を思い出しました。セルフ・コンパッション(self-compassion、自分への慈しみ、自分への思いやり)は、自分を甘やかすのではなく、悩みを抱える友人にしてあげることを、自分にもできるようにする心理療法だそうです。例えば心がほっこりする事や物を思い出し、自分を労わる時間を持つことで、自己的なケアになるそうです。
<パニックな私の森田な日々>
間違った価値観(人付き合いが上手ことだけが人として価値がある)から劣等感に陥り、対人恐怖症に陥ったが気分本位でなく、目的本位(子供のための行動)の行動に徹することで劣等感も薄まり、「社交的でなくても自分の価値を認める」ことができて、対人緊張もなくなったことがよくわかりました。現在の自分をあるがままに認めて(自己受容)、今を生きていくことが大切であることを森田は教えていますね。
<モリジイと学ぶ学習会シリーズⅡ> 2.神経質の性格特徴
モリジイさんのお話は、たいへんわかりやすく面白く、読んでいます。今回、読者の声についてモリジイさんが答えていて、良い企画だったと思いました。
・「自分の想いの事実」だけでなく「相手の想いの事実」も視界に入れる
・両面観の話「自分の性格を知り、プラスの面に気づくこととマイナスの面を受け入れることが大切」
などの言葉やモリジイさんの体験物語が印象に残りました。
<生ingセイ・イング>
メールマガジン「あずま通信」の記事でした。なかなか見る機会がないので良かったです。
五月病対策や大谷選手の話など、身近なところに森田理論が転がっていることがわかりました。生活の糧として、森田の言葉を活かしていきたいと思います。私も大谷選手の言葉から、大谷選手は「努力即幸福」を実践していることを感じておりました。実践することが大事ですね。
<私と森田と発見会>苦悩で始まり、感謝に変わる味わい深い経験
長年、強迫神経症や抑うつに苦しみながらもその症状には意味があり、それは何かを求めながら、自分への気づきができている筆者に感動しました。また当事者研究の次の言葉は、参考になりました。
① 誠実に(真剣に)向き合い、苦しむべきは苦しみ、悩むべきは悩む。
② 時々、自分を客観的に眺める。
③ 小さなことでもよいので、周りの人のために何かする。
他の症状に苦しんでいる人達にも役立つのかなと思いました。苦しみや悩みは、神様がその人に与えてくれた意味あるもので、その意味を見つけるために精進していくしかないと前向きな気持ちになりました。
<私らしく生きる>怖いと思ったことでもやってみよう
作業療法を取り入れた森田療法リカバリープログラム(ショートケア)があることを知りました。野外活動やゲームなど集談会でも実施できるものもあるかもしれませんね。
「みんな素のまま、体当たりで話し合い、自分の恥と思っていたことも共有できる安心感がありました。みんなが回復したいという同じ目的を持つなかで、学び合いや自己理解が深まりました」の言葉は、集談会の話し合いでも大切なことだなと理解しました。
<中高年のひろば> たくさんのハピネスをもらう/私の腰痛日記
ボウリングが中高年のブームになっていることは知りませんでした。模擬患者のボランティアなど、人生の後半を工夫して生きていることに感銘しました。また腰痛の話は自分も腰痛持ちなどで参考になりました。