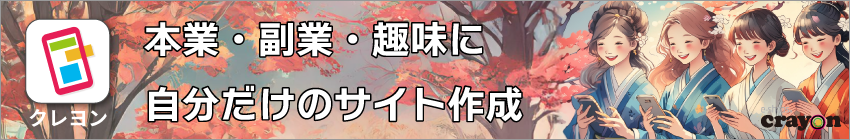
今年は、オリンピックの年で7月下旬より、パリ・オリンピックが開催されます。先日、日本の代表選手の壮行式が行われました。その中で江村選手が選手団を代表して「一歩踏み出す勇気をのコンセプトに基づいて、選手一同、新たな挑戦に向かって全力を尽くしてまいります」と述べていたニュースを見ました。
「一歩踏み出す勇気を」は、どこかで聞いた言葉だなあと思いました。そうです、生活の発見誌に見かける言葉ですね。オリンピックの代表選手でも、より高みを目指すために不安も大きいのだなと感じました。我々神経質者も、症状や不安を抱えていても、逃げないで「一歩、踏み出す」ことを忘れてはいけませんね。「一歩、踏み出す」ために集談会の話し合いや学習が、お役に立てればと思っています。
ラジオで運動生理学の先生がウォーキングを推奨していました。ウォーキングは、有酸素運動の一つで病気予防、改善の効果(糖尿病、心疾患、精神疾患など)があることは知られています。一日6000~8000歩が効果的で20,000歩以上では、悪影響があり、ダイエットには効果がないそうです。ウォーキングは、脳に対する効果があり、うつや睡眠障害に良いと言っていました。うつの人がウォーキングをすることで、うつ状態がゼロになり、プラスのポジティブなメンタルになる効果もあるそうです。そして驚いたのはWell-beingの状態が得られると話していたことです。Well-beingの状態とは、例として仕事が終わって夕日を見たとき、ああ幸せだなと感じる状態で、ありありとした自分を感じる状態(ありのままの自分?)であり、だれかとつながっていると感じる状態もWell-beingを高めるそうです。確かにウォーキングは、内に向いている心を周りの綺麗な景色を眺めることで、ああ幸せだなと感じることがありますね。毎日の忙しい生活の中で、ウォーキングが皆さんのお役にたてばと思い御紹介しました。Well-beingという言葉にも魅かれました。
今月も「がんばって」の続きです。朝、散歩で通ったお寺に掲載されていた言葉です。先月、「がんばって」の言葉について、いろいろな考え方があることを知りました。がんばっても元気や気力(うつ状態)がなくなるまで、がんばってはいけませんね。元気がなくなれば、そこまでで、どれだけがんばっても、その時点でそれ以上の事ができなくなります。その都度、体調を考えて「頑張る」ことの程度を調整し、毎日を過ごし、自分なりの森田を実践していきましょう。
ラジオで仕事で悩んでいる人に「頑張って」と言ったら、これ以上になにを頑張っていいのか分からないと言われたことを話題にしていました。うつの人には、かけてはいけない言葉のようにも言われています。気になったので、調べてみたら以下の記事がありました。
頑張り過ぎて限界に達している相手に、それ以上頑張れと叱咤激励するのは、酷ではないかという発想で、苦しいのは自分のせいじゃない、この状況は、周りのせいや相手のせいと思う他罰思考(なんでも他人のせいにしています)に陥っているためだそうです。「頑張って」と言われて嫌な気持ち(怒り)になるのは、悲しみの感情が潜んでいて、自分の状況や思いを理解してくれていないという失望感から、「頑張って」に対して拒絶が起こるそうです。「頑張って」は気を遣う言葉の一つですが、相手の気持ちを認め、心からエールを送る言葉としての「頑張れ」や、相手が努力する姿に「頑張って」は、声掛けしても良いのではと思ったりしました。「頑張って」の代わりに「応援してますよ」の方が柔らかくて、受け入れやすいかもとの記述もありました。後日、別の番組で悩みのどん底では、「頑張らないでいいんだよ」とカウンセラーに言ってほしかったとの話をしていました。「頑張って」は、なにげない元気づけの言葉ですが、相手の心情を考えた言葉を発することの難しさを改めて知ることができました。
自律神経の話で昔、3行日記を進められたことを思い出しました。
落ち込んでいる時やストレスに晒されている時に気持ちを落ち着けることとは大切ですね。
こんな状態では、自律神経が乱れて身体全体が不調になります。自律神経をコントロールするのに3行日記は役立つそうで、自律神経の第一人者の小林先生もおすすめです。3行日記は、寝る前に手書きで今日の出来事を
① 良くなかったこと(うまくいかなかったこと、嫌だったこと)
② 良かったこと(うまくいったこと、感謝したこと、うれしかったこと)
③ 明日の目標(関心を引いた些細なことでもOK)
を書くことで出来事や気持ちに対して客観的になれ、そしてポジティブな気持ちになれるようです。森田療法でも日記指導がありますね。自分の気持ちを吐き出すことが健康につながり、前向きな行動に向かわせるのかもしれません。日記が無理なら、寝る前に今日の出来事の振り返りから始めてはいかがでしょうか?
今月も逆転の発想です。先日、個性派俳優の佐藤二朗さんが「強迫性障害」であることを告白したニュースがありました。小学生の時から今まで、ずーと悩んでいたそうです。その中で「病は僕、病ゆえの力を信じよう」という言葉に惹かれました。病に苦しみながらも、病と共生し、前向きに生きていこうという力強さを感じ、同じ神経症の仲間としてエールを送りたいと思いました。
ラジオで聞いた話です。ハンセン病療養所内でハーモニカバンドを率いて多数の楽曲を残した作曲家、近藤宏一さんの話です。近藤さんも含めてバンドメンバーのほとんどが全盲で、四肢が不自由で、近藤さんは、指ではなく唇と舌先で、点字楽譜を作成、編曲し76才まで日本各地で演奏会を行ったそうです。その話の中で、全盲で四肢不自由だから、まだできることがあると考えて、近藤さんは、唇や舌先で楽譜を作り、皆なで演奏したのだとの話でした。なぜかこの言葉が心に残りました。我々も症状があるから、これもできない、あれもできないと悩んでいる時期があります。症状というハンディがあるからこそ、できることがたくさんあるのではと思いました。これも逆転の発想の一つかもしれません。但し実行には、それなりの努力が必要ですね。