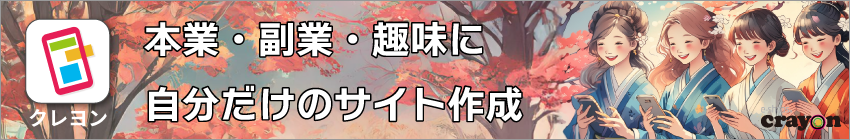発見誌2月号より
<巻頭言>
「皆で学ぶ森田理論は独りよがりになることがなく、症状克服には大きな効果があった」という言葉に集談会の意義を改めて感じました。
<特別対談>森田で老後を楽にいきるために(後編)
老後を生きるヒントをたくさん、いただきました。以下が印象に残りました。
・意欲低下の抑制のためには、セロトニン減少防止のため、肉を食べること
・病気になってできなくなったことがあっても、いろんな不自由なことがあっても、できないなりにどうやって生きていこうかと考えることは森田的
・楽しいことをやっていることが休むことになる。
・森田正馬とアルフレッド・アドラーは、非常に目的志向で、他人の気持ちは変えられないと言っている。
・変えられないことを変えようとするからみんな苦しむわけだし、できないことを素直に認めて人に、なきつきゃいいものをそうしないから苦しむ。
・日本人は周囲への同調圧力に弱いような気がします。
・日本人は残そうとするから強迫的になりがち
・大事なのはあれこれ考えていないで、まずはやってみることです。試してみて面白くなければやめればいいのです。動かないことが老化を進めます。新たな活動にチャレンジしてください。
<名文発掘>いかに実践をすすめるか(3)
実践(行動)の難しさから、困難な事態の観察分析や集談会でお互いに励ましあうなどのアイデアが記載されていました。そのなかで以下の文章が印象に残りました。
・私たちが本当に欲望にそって、どうしてもやらなくてはならない、そういうやむにやまれない欲望にのって活動している時、森田先生の言葉でいう「なりきった」時、というのは、苦もなければ喜びもない、要するに努力を努力と感じない、努力しているという意識すらない。そこに創造があり、進歩がある。それが「努力即幸福」
どうしてもやらなければの状況では、無我夢中に実践(行動)し、実践することに神経が集中している状態なのかもしれませんね。
<体験記>「あるがまま」の私へ
スピリチュアル思想を勉強した色彩療法のセラピストの先生でも、あのコロナ禍で仕事が行き詰り、強い不安感からもう一度、自分の性格を見つめ直したこと、認知行動療法による治療、そして森田療法に出会えたことなどたいへん、勉強になりました。それぞれの療法には、それぞれの良さがあり、その人その人に向き不向きもあることがわかりました。
スピリチュアル思想の「意識(心)が現実を作る」とは、森田では観念を事実と勘違いして、不安感、恐怖感に振り回されていることを言っているのかなと思いました。「事実唯真」に通じる言葉だと思いましたが?(勝手な解釈ですがーーー)
<集談会日記>
本多講師の体験談を聞いての参加者の感想が良かったです。
・症状があってもやるべきことは、やり、やりたいこともやれると自分を信じて行動していきたい。
・症状はとる必要がなく、受け入れて日々楽しむ。
・やるべきこと(役割)やりたいこと(楽しみ、生きがい)が大事。
・考えすぎず、行動あるべし
・症状はとる必要がない。不安を持ちながらも、今やるべきことをやっていく。神経質の良さを活かしてより良く生きることが大事。
<はっ犬くん オリジナル森田を読む>
自分のひがむ心に気がつかないで人を恨むのは、地球の回転を知らないで太陽が動くと考えると同様である。自分もそうですが、神経質は自己中心的のため、自分勝手な解釈で、ひがみ、ひねくれの心が非常に強いことが、この単元を読んでよくわかりました。修道を重ねなければいけませんね。
<パニックな私の森田な日々>
子供と二人でアフリカに行き、そこで一カ月半ほど滞在、生活したとの話でしたが、その行動力に感心しました。アフリカでの生活は、かつての日本がそうであったように、人々が助け合って暮らして、必要不可欠なものだけでの生活であったという文章に、今の日本には何か忘れたものがたくさんあるように感じました。
<モリジイと学ぶ学習会シリーズ> 「まとめ」のしかた
先月号の単元(治るとはどういうことか)より具体的な事柄が多く、たいへん勉強になりました。いつも感じるのですが、森田理論を知っていても実践、行動しないことには意味がありませんね。その実践、行動として日常生活を大切にし、淡々と送ることかもしれませんね。
以下の言葉が印象に残りました。
・「症状」という障害物をそのままにして、本来の欲望を達成しようと取り組んでいくと、「症状」は自然に私たちから離れていく。
・本来の欲望に従って、自分のできることを工夫しながら行動していくことじゃ。苦手なことは、無理をせず、自分ができそうな範囲でよいのじゃ。
・実践課題は少々努力を要する、しんどいなと思う程度のものが良い。
・今までは「症状」を通して自分を見ていたが、課題を実践していくうちに、現実のなかで自分がどのように動いているかが徐々に見えてくる。
・何よりも新しい課題に挑戦することで、現実生活が発展的になり、「症状」は後退していく。
<特別報告 第41回日本森田療法学会>
今回のテーマ「医療現場と生活の発見会との連帯」は、良かったのでは思います。森田療法にとって生活の発見会は、大切な活動機関と理解しています。比嘉先生の言葉の「医療と発見会との協働が更に深まり、いろいろな点で協力体制ができ、森田療法の発展・普及に大きく貢献することを期待しています」に集約されていると思いました。
依存症のほかに自助グループがあるのは、森田療法だけでは?と思っていて、心の悩みを持っている現代人は多く、悩みを分かち合えて、生涯学習としての役割も持つ機関として発展できればと思いました。
<中高年のひろば>「人生は苦」
講師として来ていただくM先生の寄稿でした。19歳の時に聞いた水谷先生の「そんなに苦しいなら苦しめばいいじゃないか」という言葉から、今の自分があることを話されていたことを思い出しました。最悪の状態を想定してことに臨むとそれ以上に悪いことが起こらないことは、自分も経験したことがあります。不安、心配が多い時ほど安心で「不安即安心」なのですね。そして次の言葉が印象に残りました。そして人生は苦が多いかもしれませんが、楽しいことも少しあると思って生きている毎日です。
・「苦しいときには苦しみ、楽しいときには楽しむ」それが「あるがまま」であり、「苦しい時に何とかそれから抜け出さねば」というのが「思想の矛盾」を生むもとになる「かくあるべし」の考えなのです。
<遊YOU>
なんでも知っている雑学博士の九州支部長のYさんの記事がまた出ていました。いろいろな事を知っているので、いつも感心しています。この雑学知識を集大成して本に纏めればと思ったりしました。